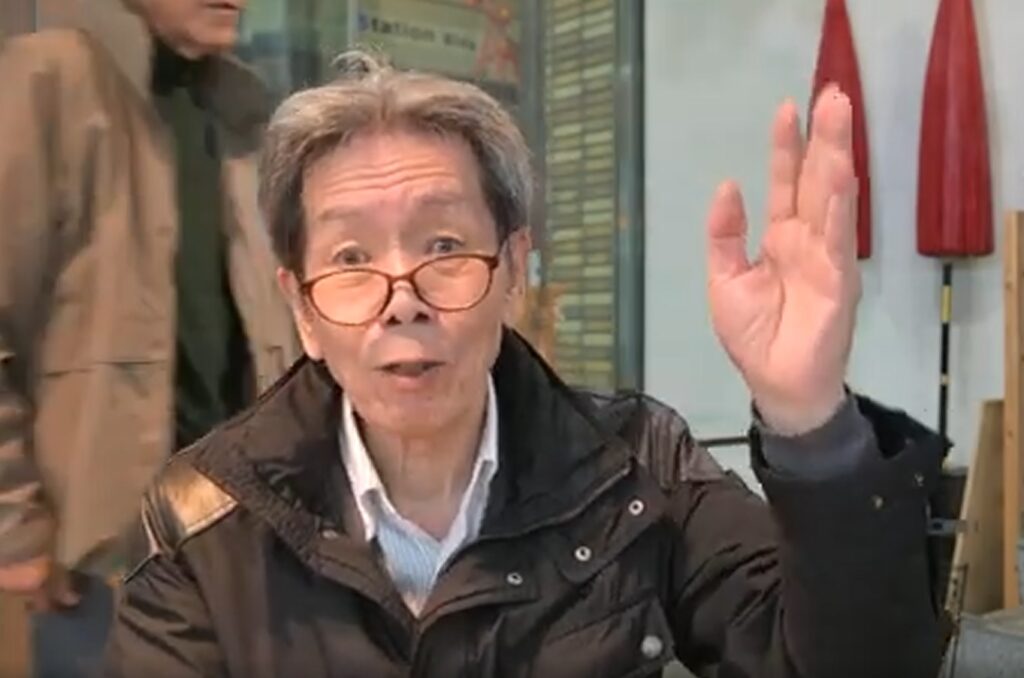
高校野球の強豪校として敦賀気比高校が頭角を現すのは1990年代。「けひ」という発音が気になっていた。その敦賀気比は2015年春、あれよあれよと勝ち進み、優勝を果たした。気比の名前は気比神社に由来する。気比神社は福井県敦賀市に鎮座する 北陸道総鎮守、越前國一之宮。空襲を免れた大鳥居は「日本三大木造鳥居」に数えられ、国の重要文化財に指定されている。また境内社の角鹿(つぬが)神社の祭神はツヌガアラシト。「敦賀」の地名の由来であると伝える。津軽は外国人の名前という事になる。
日本書紀にツヌガアラシトが登場するのは垂仁天皇二年。「額に角の生えた人が、船に乗って越の国の笥飯(けひ)の浦にたどり着いた。ある者が素性をただすと、男は次のように答えた。「意富加羅国(金官伽耶)の王子で、名はツヌガアラシトです。日本に聖皇(崇神天皇)がいらっしゃると聞きつけてやってきたのです。穴門(下関付近)に着いて、路の分からないままに海岸づたいに北海(出雲)を経て、今ここに到ったのです」といった。
ところが、ツヌガアラシトが慕った崇神天皇はすでに亡く、その後三年間垂仁天皇に仕えた。天皇はツヌガアラシトに「自国に帰りたいか」と問うと、「帰りたい」ということなので、崇神天皇の和名「御間城(みまき)」をツヌガアラシトの国名にするように言った。そして赤織絹を与え、本国に帰した。伽耶を指して「任那須」(みまな)と呼ぶのはこれが元だった。
日本書紀、垂仁天皇三年に、「新羅の王子天日槍(あめのひぼこ)来帰り」とある。新羅の王子が日本に帰化しようとやってきたというのだ。
ところが、古事記には天之日矛(あめのひぼこ)がツヌガアラシトと重なる人物として登場する。そして、神功皇后が天之日矛の子孫であると書かれている。神功皇后は三韓征伐を行った伝説上の人物で、仲哀天皇と共に九州征伐に向かう前に、敦賀にいた。そしてその子である応神天皇(第15代)は即位の前に敦賀にやってきて気比神社の神、イザサワケノ命と名前を交換したとあるから、単なる神話として放っておけないのである。
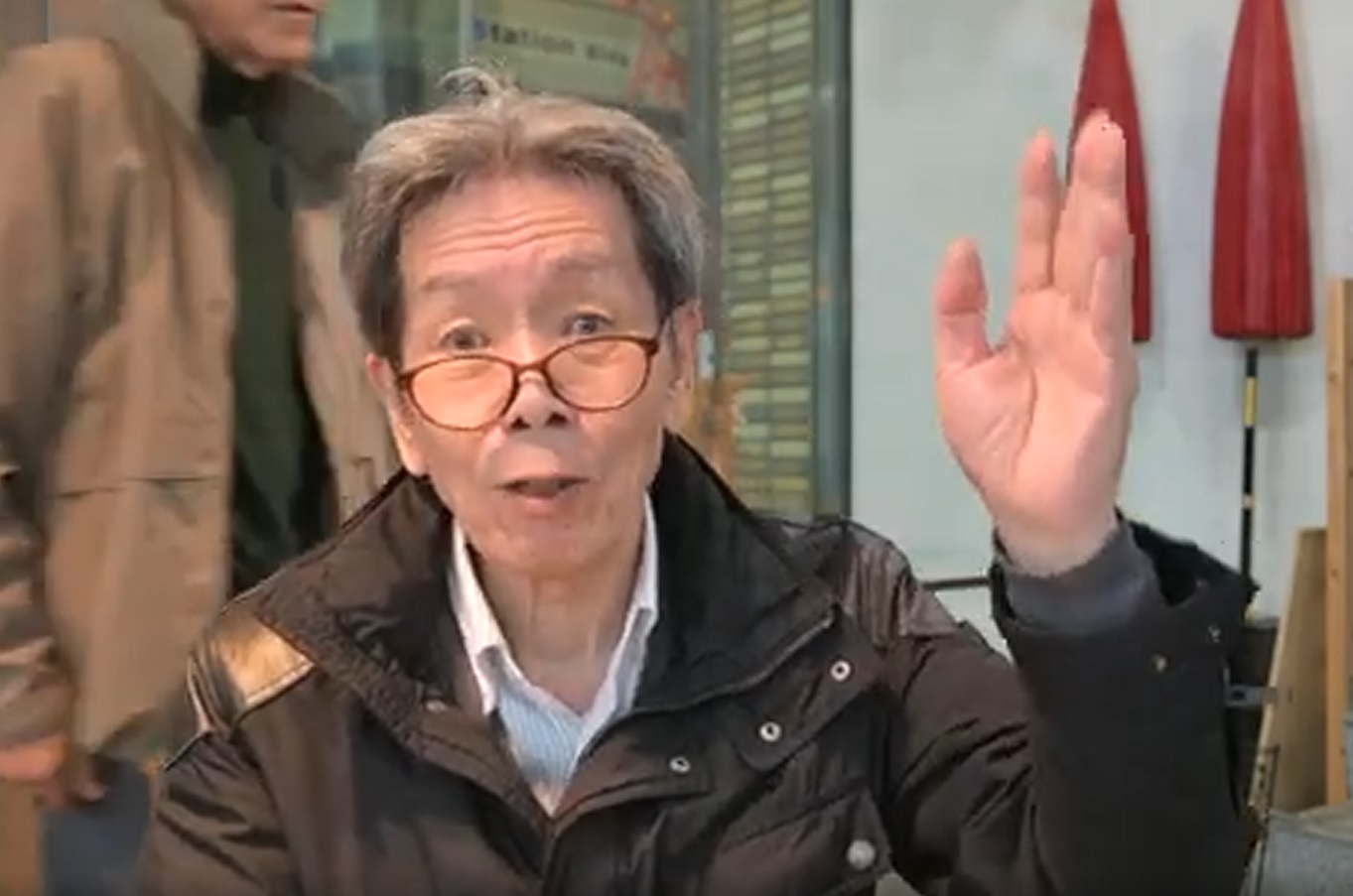
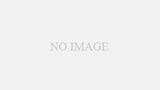

コメント